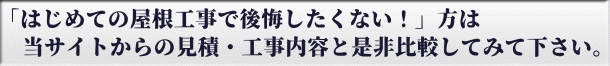屋根のDIY工事は可能か
屋根工事をDIYで行う際に必要な知識・技術
屋根の構造と役割を理解する必要がある
屋根は住宅の重要な部分であり、外部環境から建物を保護する役割を担っています。
したがって、屋根工事をDIYで行うには屋根の構造、役割、そしてそれらが密接に関連している仕組みを十分に理解する必要があります。
屋根は大きく分けて以下の3つの要素で構成されています。
| 要素 | 役割 |
|---|---|
| 屋根材 | 雨や風、UVなどの自然要素から建物を保護します。 |
| 下地材 | 屋根材を支え、水滴の浸透を防ぎ、断熱性と防水性を向上させます。 |
| 構造材 | 屋根の形状を保ち、強度と安定性を確保します。 |
これらの要素に関して強固な知識を持たなければ、施工ミスにより住宅全体に重大なトラブルが発生しかねません。
たとえば、屋根の角度や形状に応じた適切な材料選びと取付手順を理解していないと雨漏りや熱効率の低下などの問題が起こります。
雨漏りや断熱などの問題点への対応スキルを身に付ける
屋根の防水性と断熱性は特に重要なポイントです。
例えば、防水処理が不十分だ雨漏りが発生し、木材の腐敗や建物内部の劣化が進行します。
そうなると早い段階での修理が必要になり長期的なコストがかさむ結果を招きます。
また、断熱性が不十分な場合、季節ごとの快適性に影響が及び、エアコンや暖房への過剰な依存による光熱費の増加を引き起こします。
これらの問題を防ぐためには、以下のような専門知識やスキルが必要です。
■ 防水処理に使用する防水シートの選定と設置方法
■ 断熱材の種類(グラスウール、ポリスチレンフォーム等)とその適切な配置
■ ガルバリウム鋼板など特定の素材特性に基づいた加工や取り付け方法
たとえば、北海道のような寒冷地では断熱材の厚さを厚めに設定する必要があり、適用する製品の選定が重要です。
こうした地域特性も考慮した屋根の工事が必要です。
DIY屋根工事に伴う安全面の課題
高所作業における特有のリスク
屋根での作業では、安全性を考慮する必要があります。
日本国内では、建築現場や住宅の屋根施工中の怪我が多く、高所作業特有の危険性があります。
また、建築業の事故データを反映した厚生労働省の報告によると、作業員の転落事故の中でも傾斜面での事故が全体の約25%を占めています。
そのため適切な装備に加え、さらに安全性の高い足場設置や補助者を周囲に配置することが重要です。
適切な安全対策の必要性
DIYであっても安全装備の使用は必須です。
以下のポイントに注意して装備を整えましょう。
■ 落下防止用命綱を利用した装備(ハーネスと安全帯)
■ グリップの効いた滑り止め付の作業用靴
■ 衝撃吸収性があるヘルメット
■ 目を保護するためのゴーグル
これらの装備を正しく使うだけでなく、実際の現場でも的確に対応できる能力を身につけることが大切です。
DIYを断念したお客様からの依頼例。

現在ログハウスをセルフビルド中だが、屋根合板を張り終えたところ。勾配がきつく(31度くらい)足場も設置していないため、自分で施工するのは難しいと判断した。
アスファルトルーフィングを軒先に張っていたが、風にあおられ破れてしまい断念した。
棟換気用に屋根合板の棟部分に数センチの開口部あり。アスファルトルーフィングとアスファルトシングル(オークリッジスーパー)の作業をお願いしたい。
なるべく安価に作業頂ける業者さんを希望します。とのご依頼でした。
お客様は、オークリッジスーパーを購入されていましたが、その後、適切な屋根材を提案して欲しいとのご希望で、ストーンチップのディプロマットで工事させて頂いた埼玉県の事例です。
DIYでガルバリウムを使用した屋根工事のポイント
ガルバリウム鋼板とは何か
ガルバリウム鋼板の特徴と利点
ガルバリウム鋼板は、高い耐久性と防錆性能が特徴の金属製屋根材で、日本の屋根工事で特に人気があります。
これはアルミニウム、亜鉛、シリコンを成分とする合金で作られており、一般的な亜鉛メッキ鋼板よりも耐候性が向上しています。
また、軽量性もこの素材の重要な特徴です。
建物や基礎の負担を軽減し、耐震性を高めることができます。
そのため、強さと軽さのバランスが取れた素材として、住宅や倉庫などの幅広い建築物に使われています。
このような特長から、多くのDIY愛好者が手軽に扱える素材として選んでいます。
他の素材との違い
日本で使用される一般的な屋根材には、スレートや瓦などが挙げられます。
ここでは、これら他の素材とガルバリウム鋼板の違いを詳しく比較します。
| 素材 | 利点 | 欠点 |
|---|---|---|
| スレート | 価格が安い、作業性が高い | 耐久性が低く、割れや苔の問題が発生しやすい |
| 瓦 | 美観に優れ、耐久性が高い | 非常に重く、施工に専門技術が必要 |
| ガルバリウム鋼鈑 | 軽量で耐久性と防錆性能が高い、DIYでも扱いやすい | 金属特有の断熱性に劣るため、追加の断熱材が必要 |
このようにガルバリウム鋼板は、スレートや瓦とは異なるバランスの良さが特徴です。
特にDIYにおいては、強度と軽量性、そしてその施工性の高さが大きな利点と言えるでしょう。
DIYでガルバリウムを使用する際の準備
必要な工具と材料
ガルバリウムをDIYで扱うためには、適切な工具と材料を揃えることが重要です。
以下はその一覧と主な用途です。
| 工具/材料 | 用途 |
|---|---|
| 電動ドライバー/インパクトドライバー | ガルバリウム鋼板をビスで固定するために使用 |
| 専用ビス(ステンレス製)とパッキン | 防錆性を維持しながら、強固な固定を実現する |
| 電動カッターまたは金切り鋏 | ガルバリウム素材を必要なサイズに切断する際に使用 |
| 防水シート/ルーフィング | 屋根全体の防水性を高めるために敷設 |
| 安全帯、ヘルメット、滑り止め付きの作業靴 | 高所作業時の安全を確保する装備 |
これらをすべて揃えることで、安全かつ効率的にDIY工事を進めることができます。
購入前に必要な道具をリスト化し、ホームセンターやネットショップなどで確認してください。
適切な施工手順の基本
ガルバリウムを使ったDIY屋根工事では事前準備と正確な手順が欠かせません。
基本的な施工手順をご紹介します。
1. 作業を開始する前に、天候や安全装備を確認する。
2. 既存の屋根材が損傷している場合は撤去し、清掃を行う。
3. 屋根の下地状態を確認し、防水シートを敷設する。
4. 防水シートの上から、必要なサイズに切断したガルバリウム鋼板を配置する。
5. 専用ビスを使用して、規定の間隔ごとにしっかりと固定する。
6. 継ぎ目や隙間に防水シーリング剤を塗布し、完全な防水性を確保する。
7. 全体を確認し、不備があれば修正して完成。
修理箇所が多い場合や高度な技術を要する作業の場合は、プロに相談して下さい。
必要があれば、工程ごとに写真や動画で記録を残し、予期せぬ問題に対応できるように準備しましょう。
ガルバリウムを使ったDIY屋根工事の完成イメージ
事例としての施工例
一般的な施工例として、古いスレート屋根をガルバリウムに張り替えるケースがあります。
この場合、施工期間は通常1〜2週間程度で完了します。
例えば、YouTubeや施工業者の公開している事例動画を参考にすることで、流れを正確に把握できるでしょう。
専門職人による参考例としてはこちらをご覧ください:ガルバリウム鋼板の施工事例(屋根無料見積.com)
期待できる耐久性
ガルバリウム鋼鈑は錆びにくい特性があるため、長期間美しい外観を保つことが可能です。
また、カラーバリエーションとデザインの柔軟性により、住宅全体の美観を向上させます。
ガルバリウム鋼板を使用した屋根は、高い耐久性がありますが、DIYで工事した場合の屋根寿命は技術的な問題があるため10年程度と考えておくのが妥当でしょう。
DIY屋根工事の限界とプロに依頼すべきケース
DIYで対応可能な範囲
補修程度の小規模工事
DIYで対応可能な工事は、一般的に規模が小さく、損傷箇所が限定されている場合に限られます。
例えば、瓦が剥がれた場合の一部分交換や、スレート屋根の固定が緩んでいる部分の再固定など、小規模な補修作業が主な対象です。
特に、雨どいの清掃や、屋根表面の苔や汚れを除去する作業など、建物の保守的な意味合いが強いものは、DIYでの取り組みも一般的です。
ただし、これらの作業でも適切な道具や安全策が必要になるため、軽装備で対応するのは避けるべきです。
また、こうした小規模な作業であれば、自分で施工しながら屋根の状態を観察することが可能です。
しかし、屋根の勾配が急な場合や高所作業に慣れていない場合は非常に危険です。
そのため、自信が持てない場合や不安を感じるようであれば、早い段階でプロの助けを求めるべきでしょう。
材料交換など単純作業と張り替え
DIYで挑戦しやすい作業の中でも、屋根材の交換などの単純作業は、手順を守り必要な装備を整えれば比較的安全に実施できるとされています。
しかし、スレート屋根の割れた部分を取り外して取り換える修理などは専用工具が必要で専門ノウハウがないと不可能です。
また、ガルバリウム鋼板のように軽量な屋根材を用いた張り替え作業も可能ですが、基本的な施工を守らないと風の影響で屋根材が飛ばされる可能性や雨漏りが発生するリスクがあります。
さらに、屋根の土台や構造自体に影響を与える作業に及ぶ場合は注意を要します。
既存の建材を除去する際に、屋根全体の強度が低下したり、逆に素材を過剰に固定して構造が脆弱化するリスクもあるため、DIY作業は元の構造を維持できる程度に留めることが重要です。
プロに依頼する必要がある工事
構造部分の修理や屋根全体の張り替え
屋根全体の張り替えや、下地の補強が必要になる場合は、プロの業者に依頼するのが最適です。
これらの作業は、大規模な工事であると同時に専門知識が必要で正確な診断と精密な施工が要求されます。
例えば、瓦屋根を全面的にガルバリウム鋼板へとリフォームする場合、屋根材の撤去から新しい屋根材の取り付け、防水工事に至るまで多くの工程が発生します。
この際、基礎となる防水シートの敷設やガルバリウム本体・部材役物を適切に施工しないと、施工後に問題が発覚することがあります。
また、建築基準法に関連する許認可が必要になるケースもあります。
そのような工事になる場合は、専門資格を持つ屋根工事のプロ業者に依頼し、確実に対応してもらうことで法律を遵守し安全性を確保できます。
雨漏りや損傷が深刻な場合
雨漏りのような建物全体に影響を及ぼす問題が発生している場合、DIYでは解決が困難であることが一般的です。
見た目で状況を判断するのは難しく、部分的な補修だけでは根本的な問題を解決できない恐れがあります。
例えば、屋根の内側や下地部分がすでに腐食している場合、それを放置すると建物の寿命にまで影響を与えかねません。
屋根材毎の正しい工事方法を知るプロの専門職人であれば、雨漏り原因になっている既存屋根における施工の問題点を探り出し、目に見えない劣化や損傷箇所を正確に見つけます。
これに基づき適切な修繕計画が立てられるため、問題を根本から解決できるのがプロの専門職人に依頼する大きな利点です。
DIYとプロ施工の費用・コスト比較
DIYの初期投資と長期コスト
DIYでの施工は一見すると費用を大幅に削減できるように思われがちですが、実際には意外なコストが発生するケースが多々あります。
まず、工具類(インパクトドライバーや釘打ち機など)の購入費用、安全装備(安全靴やヘルメット、安全ベルトなど)の準備費用が必要です。
施工後に問題が発生した場合の手直し費用や、雨漏りの再発による家具の買い替え、建物内部の修繕費用などが発生した場合、長期的にはDIYの方が高額となる可能性があります。
プロ施工のメリット
一方、プロに依頼した場合、初期費用はDIYよりも高額になりますが、高い技術力、施工精度、そして安心感が得られます。
また、プロに依頼することで屋根工事専門業者から助言を受けられます。
DIY屋根工事を行う際の注意点
施工後のメンテナンス
定期点検のスケジュール化
DIYで施工した屋根を長期的に維持するために定期的なメンテナンスが必須です。
プロの施工と比較すると、DIYではどうしても初期段階での施工精度に限界があるため、問題が起こる前に対応する必要があります。
以下のスケジュールを参考に点検を行うことをお勧めします。
■ 年に2回の目視点検(春と秋がおすすめ)。
■ 台風や大雨の後には必ず屋根の状態を確認。
また、具体的な確認ポイントとして、以下が挙げられます。
■ 屋根材のずれや浮き、破損
■ 釘やネジの緩み
■ 隙間からの雨水の侵入
早期発見ができれば、コストを抑えた修理が可能です。
点検後、不具合が見つかった場合は適切な修理方法を検討してください。
問題発生時の対応方法
万が一の不具合が発生した場合は、まずは状況を正確に把握しましょう。
軽微なトラブルであればDIYでの補修が可能ですが、深刻な破損や修理が難しい場合は無理をせずプロに依頼することが安全です。
以下は、対応の簡単な判断基準です。
| 状況 | 推奨される対応 |
|---|---|
| 屋根材の浮き・欠損 | DIYでの補修が比較的容易。正しい部品を使用すること。 |
| 雨漏りが広範囲にわたる | 専門業者に依頼する。構造に影響を及ぼす恐れがある。 |
| 全体的な劣化 | 業者による全面施工を検討するべき。 |
修理に必要なコストや手間を正確に見積もり、安全と品質を優先して判断を行いましょう。
事前に十分な情報収集を行うことの重要性
DIY初心者が陥りやすい落とし穴
DIY初心者に多い失敗例としては、施工手順の誤りや材料選定のミスが挙げられます。
これらのミスは余計なコストや時間を浪費する原因なるだけでなく施工後に重大な問題を引き起こす可能性もあります。
例えば以下のようなケースが挙げられます。
■ 固定が甘く、ガルバリウム鋼板が強風で外れてしまう。
■ 屋根本体や役物の切断・取り付けの問題で雨漏りしてしまう。
これは業者に頼んでも起こりえる問題のためDIYで工事する場合は特に注意が必要です。
こういった施工ミスを避けるためには、信頼できる情報源を参照し、しっかりと事前学習を行うことが重要です。
インターネットや書籍には多くの情報がありますが、誤った知識を参考にしないことが成功のカギです。
以下のような情報源を活用することで、正確な知識を得られます。
施工経験者のレビューや実績があるDIY専門書籍などの情報源を活用することで、正確な知識を得られます。
さらに、建築関連の専門業者が公開する動画や相談サービスも積極的に活用して、正しい知識を持った状態で準備しましょう。
この記事を書いた人

- 屋根無料見積.com運営責任者
-
屋根材メーカー(積水化学工業)直属の屋根診断士として活動し屋根工事・見積り経験35年・5,000件以上。
屋根工事の裏側を知り尽くした運営責任者が経験で得た専門情報をお伝えします。
また、専門資格や専門技術を持つ屋根職人が減った影響で起きている「低品質な屋根工事による被害」を減らすことを目的に日本屋根業者サポート協会に加盟する屋根職人とお客様との橋渡しをする活動を行っており、悪質業者による被害を減らすため900件以上の屋根相談、ボッタクリ被害を減らすための見積書診断サービスを180件以上行っています。